ひむか行政書士事務所は
あなたのやりたいことを
応援します。
事業を始めたい 自分のお店を持ちたい
自動車の手続きをしたい
終活を始めたい
法人を設立したい
外国人を雇用したい
契約書を作成したい
事業を始めたい!
事業開始に必要な免許や許可の取得をお手伝いします。
■ 建設業
一定規模以上の建設業を営む場合は都道府県知事や国土交通大臣の許可が必要です。
建設業許可には一般建設業の許可と特定建設業の許可があり、元請けとして大きな工事を請け負う場合には特定建設業の許可を取得する必要があります。
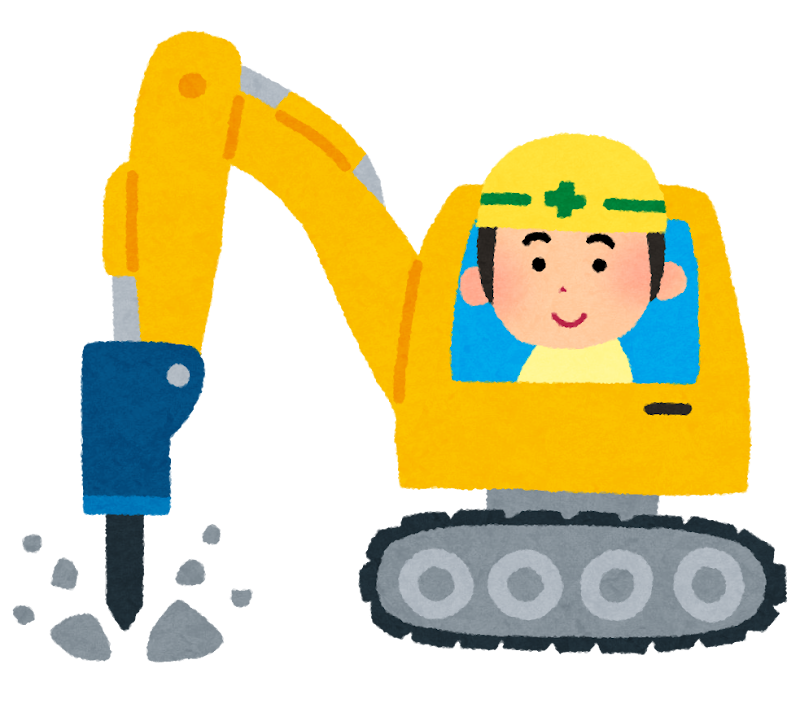
■ 宅地建物取引業
不動産業を開業するには、宅地建物取引業に係る都道府県知事や国土交通大臣の免許が必要です。
宅地建物取引業とは、宅地又は建物の売買(交換)やこれらの売買(交換)賃貸の代理、媒介を業として行うことをいいます。

■ 運送業
バスやタクシー等の旅客自動車運送事業(一般乗合、一般貸切、一般乗用、特定旅客)、トラック等の貨物自動車運送事業(一般貨物、特別積合せ、特定貨物)を始めるためには、国土交通大臣の許可が必要です。貨物軽(黒ナンバー)の場合は許可ではなく届出になります。

■ 倉庫業
他人から寄託を受けた物品を倉庫において保管する倉庫業を営むためには、倉庫業法に基づく登録を受ける必要があります。
保管する物品に応じた倉庫施設の基準をクリアした倉庫であること、倉庫毎に一定の要件を備えた倉庫管理主任者を選任すること等が必要となります。

■ 産業廃棄物処理業
工事現場や工場など事業活動により排出される産業廃棄物の収集運搬や処分を行うためには、都道府県知事の許可が必要です。
ページトップに戻る
自分のお店を持ちたい!
開店に向けた各種の手続きをお手伝いします。
■ 飲食店
飲食店を開業するには管轄保健所の許可が必要です。当該許可を得るためには食品衛生責任者1名を必ず置くとともに、施設基準を満たさなければなりません。また、収容人数が30名以上の場合は防火管理者を選任する必要があります。

■ 酒類販売
お酒を販売するには酒類販売業免許が必要です。このうち一般の消費者を対象に販売する場合は酒類小売業免許で、主に酒販店のように店頭でお酒を販売する一般酒類小売業免許とインターネット等で販売する通信販売酒類小売業免許の2つに分けられます。
飲食店で開封したお酒を提供する場合は酒類販業免許は不要で飲食店営業許可の範囲で提供が可能です。

■ 古物商
中古品やリサイクル品等の古物の売買を業として行う場合には、都道府県公安委員会の許可が必要です。「古物」とは、一度でも使用されたか使用のための取引がされた物品をいい古物営業法で13品目に分類されています。
「業として」とは、利益を出す意思をもって継続的に行うことをいいます。自分の不要になった衣類等をフリ-マーケットで販売するような場合は古物商の営業許可は必要ありません。

ページトップに戻る
自動車の手続きをしたい!
自動車の保有に関する面倒な手続きをお手伝いします。
■ 自動車の各種登録申請と車庫証明
自動車の購入や名義変更、転居の手続き等をする場合には、使用の本拠地を管轄する運輸支局に自動車登録申請を行う必要があります。
これらの申請の際には車庫証明(自動車保管場所証明)が必要なため、車庫(保管場所)の住所地を管轄する警察署に出向いて申請を行わなければいけません。

■ 出張封印(丁種封印)
自動車の新規・移転・変更等の各種登録を行う場合や、希望ナンバー・図柄入りナンバーへの変更を行う場合は、平日の昼間に陸運支局のナンバーセンターに車を持ち込んでナンバープレートの交換と封印を行う必要があります。
丁種会員の行政書士であればお客様の車庫等まで出張してプレートの交換と封印まで行うことが可能です。
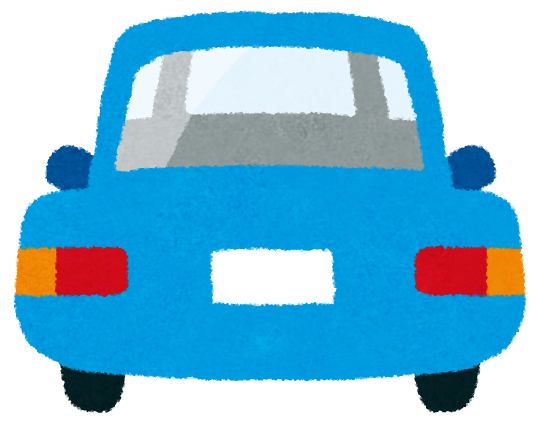
■ 特殊車両通行
クレーン車やトレーラー連結車など構造が特殊である車両、貨物が不分割で荷台をはみ出して走行する車両等、車両制限令に定める制限値を超えた車両の通行には国土交通大臣の許可が必要です。
ページトップに戻る
終活を始めたい!
自分らしい終活の準備をお手伝いします。
■ 遺言書作成
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類の方式があります。自筆証書遺言は紙と筆記用具と印鑑さえあればいつでも手軽に作成できますが、紛失等のリスクがあります。
一方、公正証書遺言は最も安全性が高い方式ですが、証人の確保や公証役場の手数料等の負担も発生します。
それぞれにメリット・デメリットがあり、十分な検討を重ねて最も適した方式を選択する必要があります。
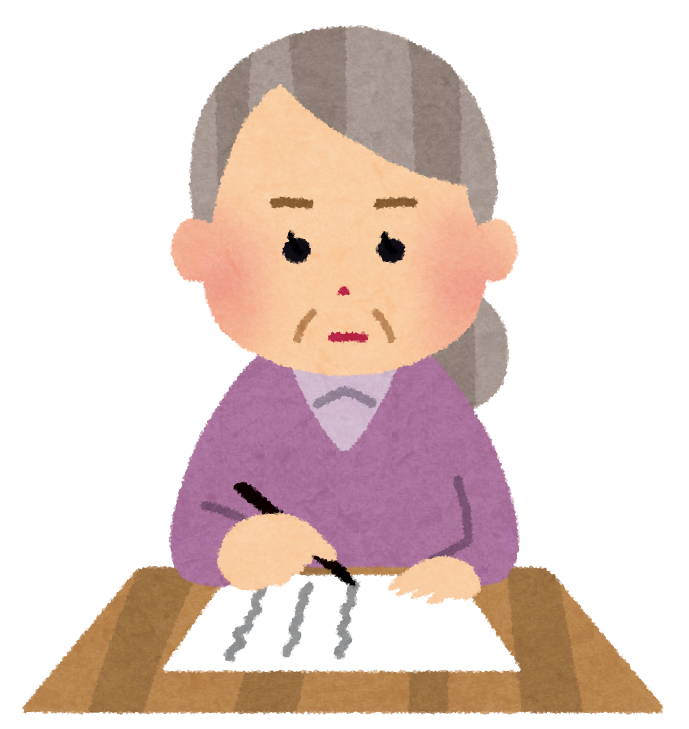
■ 民事信託契約
財産を持っている人(委託者)が、家族等の信頼できる人(受託者)に財産を託し、受託者は信託目的を達成するために財産の管理や処分を行う、等の契約を「民事信託契約」といいます。
管理する財産から生じた経済的利益は委託者やその他の者を(受益者)と指定して帰属させます。民事信託は、財産の所有と管理を分離することができるため、認知症対策や生前の財産管理対策として有効であるほか、遺言と同様の資産承継機能も有しており、近年注目されているしくみです。

■ 遺産分割協議書作成
遺産分割協議書とは、遺産分割協議で合意した内容をまとめた書類です。遺産分割協議には相続人全員が参加して、話し合いにより遺産分割の方法と相続の割合を決めていきます。
遺産分割協議により相続人全員の合意が得られたら、その内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。預金の払い戻しや不動産の名義変更等の具体的な財産処分の手続きには基本的に遺産分割協議書が必要です。
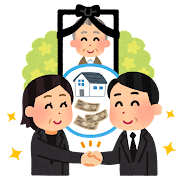
ページトップに戻る
法人を設立したい!
新しいことにチャレンジする法人の設立をお手伝いします。
■ 会社設立
会社法における会社には、株式会社と3つの持ち株会社(合名会社、合資会社、合同会社)があります。一般的な株式会社の場合は、会社の目的などを定めた定款を作成し、出資を募り、取締役を選任し、設立登記を行うことにより会社が成立します。
中小の株式会社では、株主と取締役を一人で兼ねるいわゆる「一人会社」も設立が可能です。また、現在は資本金1円でも会社を設立することができます。なお、有限会社は、現在では株式会社の一種に位置づけされ新規に設立することはできません。
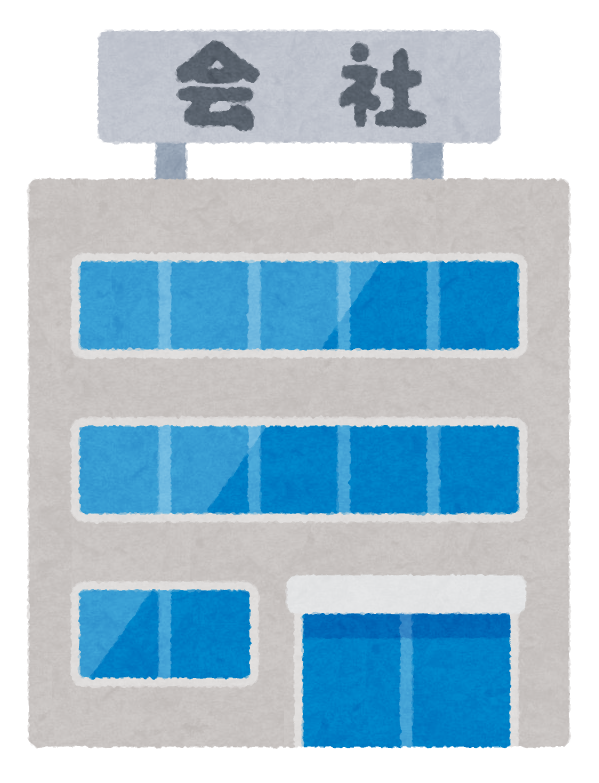
■ NPO法人設立
NPO法人は特定非営利活動促進法に基づき法人格を付与された法人でボランティア活動など市民の自由な社会貢献活動を行うことを目的として設立されます。特定非営利活動は20種類の分野に該当する活動であり、不特定多数のものの利益に寄与することを目的とするものです。NPO法人を設立するためには、所轄庁である都道府県知事(一部政令指定都市)の認証を受ける必要があります。
ページトップに戻る
外国人を雇用したい!
多文化共生社会への取組をお手伝いします。
■ 在留許可取得
「在留資格」とは、外国人が日本で行うことができる活動等を類型化したもので、法務省(出入国管理庁)が外国人に対する上陸審査・許可の際に付与する資格です。
現在、在留資格には、活動系資格25種類と身分・地位系資格4種類の合計29種類があります。外国人が日本に滞在(短期滞在を除く)するためには、必ず1つの在留資格を有している必要があります。原則として外国人が日本でできることは、許可された在留資格に対応する活動に限られています。

ページトップに戻る
契約書を作成したい!
専門性の高い事務をお手伝いします。
■ 契約書作成
契約は一部の契約を除いて当事者の合意のみで成立します。しかしながら、契約による合意事項を明確にし、当事者が契約を守り紛争の発生を予防するために、通常は契約書の作成が行われます。契約書作成にあたっては、合意内容をもれなく正確に記載するとともに、契約締結後の状況の変化に対応できるように様々な想定を尽くして作成しておく必要があります。

■ 内容証明郵便作成
内容証明郵便とは、郵便局が差出人・宛先・内容・差出日を証明する郵便です。法律や契約に基づく通知・請求書等を発送するとき、時効の完成を阻止したいとき、相手方に対して強いメッセージを伝えたいときなどに送付します。
内容証明郵便は書き方や書式が決められており、郵便局で5年間保管されます。内容証明郵便の発送は集配郵便局及び支社が指定した一部の郵便局のみ取扱っています。

